「赤ワインは健康にいい」と聞くと、毎日飲んでも大丈夫なの?と思ってしまいますよね。
でも、アルコールの“適量”を超えると逆効果になることも。
この記事では、厚生労働省の指針や最新研究をもとに、健康的にワインを楽しむための量・頻度・習慣を解説します。
“ワイン好き夫婦”のやすさん&トコちゃんが、食卓目線で「ちょうどいいワインの距離感」を語ります。
 やすさん
やすさん数字で見ると、1日180mlが“健康的な上限”なんだ。



ふむふむ、グラス1杯くらいが“ちょうどいい幸せ”ね!
まずは“全体の地図”で基礎を押さえたい方へ。→ 👉 初心者向け・安ワインの選び方まとめ
本当に失敗しない1本を探すなら、【1000円台で買えるワインおすすめランキングTOP10】をご覧ください
ワインの「適量」はどれくらい?
ワインを健康的に楽しむために、まずは「適量」のラインを知っておくことが大切です。数字で見ると、意外と少ないと感じるかもしれません。
1日180ml=グラス1〜1.5杯が目安
厚生労働省が示す「節度ある適度な飲酒」の基準は、1日平均の純アルコール量で約20gです。
アルコール度数12%のワインの場合、この純アルコール量20gに相当するのは約180ml。一般的なワイングラスで1杯から1杯半程度が目安となります。
ちなみに、750mlのワインボトル1本には純アルコールが約80g(純アルコール20gの4日分!)含まれています。もし毎日ボトル1本を空けているなら、それは明らかに「飲みすぎ」の状態です。



ボトル1本は“週分”なんだ。毎日だと過剰確定だね。



毎日ボトルは“研究”じゃなくて“実験事故”ね!
“危険”かどうかの判断軸を先に整理。→ 👉 安ワイン安全ガイド
男女差に注意
アルコールの適量には個人差がありますが、特に性別による差は大きいとされています。
- 男性:グラス1〜2杯(150〜300ml)
- 女性:グラス1杯(100〜150ml)以内が望ましい
一般的に、女性は男性に比べて体格が小さく、アルコールの分解速度も遅い傾向があります。また、ホルモンの影響も受けるため、より少ない量が推奨されます。
健康効果は“適量前提”でのみ
「赤ワインは健康にいい」と聞くと、ポリフェノールの抗酸化作用や血流改善といった効果を期待しがちです。
ただし、これらの効果はあくまで“適量を守った場合”の話。「健康のために飲む」というのは誤りです。
WHO(世界保健機関)や医学雑誌『Lancet』の近年の報告では、「アルコールに安全な飲酒量は存在しない」という見解も強まっています。
毎日飲むとどうなる?
適量であっても、毎日アルコールを摂取し続けることにはリスクが伴います。体、特に肝臓への影響を知っておきましょう。
肝臓への負担と回復の仕組み
アルコールの分解は、すべて肝臓が担っています。毎日アルコールを摂取すると、肝臓は休む暇なく働き続けることになり、負担が蓄積します。
これが続くと、脂肪肝や肝機能の低下につながる可能性があります。また、分解の過程で生じるアセトアルデヒド(二日酔いの原因物質)も体に蓄積しやすくなります。
肝臓が回復するためには、アルコールを摂取しない時間が必要です。理想としては「休肝日」を週に2日程度設けることが推奨されます。



肝臓も24時間営業じゃ疲れるから、定休日が必要なんだ。



休肝日って、体のための大事なシフト表なのね!
飲みすぎがもたらすリスク
ワインの飲みすぎは、肝臓以外にも様々な健康リスクをもたらします。
- 睡眠の質の低下(寝つきは良くても、眠りが浅くなる)
- 高血圧
- 中性脂肪の増加
また、習慣化することでアルコールへの依存リスクも高まります。
「飲まないと落ち着かない」「寝る前に一杯飲まないと」と感じ始めたら注意信号です。「今日は飲まなくても平気?」と自分に問いかけるのが、簡単なセルフチェックになります。
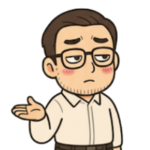
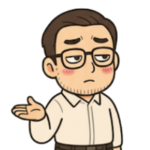
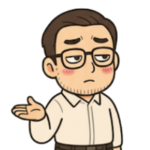
“飲まないと落ち着かない”って思ったら危険サインなんだ。
健康的に続けるコツ
リスクを理解した上で、上手にワインと付き合っていくコツを紹介します。
- 食中酒として飲む: 食事と一緒に、ゆっくり・よく噛みながら飲む。
- チェイサーを用意する: ワインと同量以上の水や炭酸水(チェイサー)を必ず併用する。
- 量を可視化する: 「ボトル1本を2〜3日に分ける」と決めたり、デキャンタで飲む分だけ移すなど、量を意識します。



うちは「今日はボトルの半分まで」ってルールにしようかな。
無理せず続ける“ワイン習慣の整え方”
「わかってはいるけど、つい飲んじゃう…」という方へ。無理なく健康的な習慣を続けるための工夫を見ていきましょう。
週単位でメリハリをつける
「毎日飲む」のではなく、「飲む日」と「飲まない日」をあらかじめ決めておくのが効果的です。カレンダーに印をつけるのも良いでしょう。
- 例:月〜金は1杯だけ、土曜は休肝日、日曜は家族で乾杯
“無意識の飲酒”(疲れたから、なんとなく、など)を避ける工夫が大切です。
開栓後の保存術で“ダラ飲み”防止。→ 👉 コルクとスクリューの使い分け



よし、「水曜日はお休み!」ってカレンダーに書き込んどこ。



最近は、予定管理アプリで“肝臓のスケジュールも管理”できる時代だね。
食事とセットで楽しむ
ワインは「食中酒」として楽しむのがベストです。食事と一緒に飲むことで、アルコールの吸収が緩やかになり、急激に酔うのを防げます。
空腹時の飲酒(いわゆる「空きっ腹に酒」)は、胃腸への刺激が強く、アルコールの吸収も早まるためNGです。
食事と一緒なら、自然と飲むペースもゆっくりになり、結果的に摂取量を減らすことにもつながります。
“食中酒運用”でからだに優しく。→ 👉 ペアリング完全ガイド



ワインは“飲む”ものじゃなく、“味わう”お酒だからね。
無理せず“飲まない日”を楽しむ
休肝日を「我慢の日」と捉えると辛くなります。「飲まない日=リセット日」として、別の楽しみを見つけましょう。
- ノンアルコールワインや、上質なブドウジュースを炭酸で割る。
- いつもより少し良いお茶やハーブティーを楽しむ。
- “飲まない日”は食生活全体を整える日と決める。
翌朝の体調の良さや、目覚めのスッキリ感を記録してみるのも、休肝日を続けるモチベーションになります。



最近のノンアルワインって美味しいし、気分は十分ワイン気分よ!
ノンアルワインの3銘柄を徹底検証👉【徹底検証】ノンアルコールワインは美味しい?人気3銘柄の評判を調べてみた
まとめ
ワインを健康的に楽しむためのポイントをまとめます。
- ワインの適量は1日180ml(グラス1〜1.5杯)までが目安。
- “毎日”ではなく、「週に数日はお休み(休肝日)」を。
- 大事なのは「飲むこと」より「飲み方」。
- ワインは“長く楽しむ趣味”として、体と相談しながら付き合おう。
“飲む量より、飲まない勇気”。
我が家の冷蔵庫には「今日は我慢!」のメモが貼ってあることもあります。
ワインは逃げません。肝臓をいたわりつつ、また明日おいしく乾杯しましょう🍷



研究は長く続けたいけど、飲みすぎは研究の終わりが早いからね。



そうそう!明日もおいしく飲むために、今日はお休み、ね!
正しい知識で健康的に飲もうネ!→ 👉 初心者向け・安ワインの選び方まとめ
編集後記
“食事と一緒に”を徹底するならこちら。→ 👉 ワインとおつまみのペアリング完全ガイド
健康的に楽しめる“当たり銘柄”を横断で把握。→ 👉 【2025年最新】1000円台で買える安ワインおすすめランキングTOP10
家飲みの“買い場”起点で計画飲酒。→ 👉 スーパー別おすすめ安ワインまとめ
























